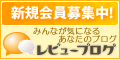[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Editorial: Japan must lead in NPO revolution
社説:震災1年・未来のために 「NPO革命」を進めよう
We have reached the one-year anniversary of the Great East Japan Earthquake and tsunami -- let us pray once again for the souls of those who lost their lives to the disaster, and for the recovery of the devastated Tohoku region and Japan as a nation.
東日本大震災の発生から、きょうで1年を迎えた。改めて多くの犠牲者の冥福を祈るとともに東北、そして日本の復興を誓う日としたい。
The fact that victims deeply affected by the disasters and the ensuing nuclear crisis have made it this far despite the sluggish response of the central government is a testament to their perseverance and the backbreaking efforts of local governments. There is, in addition, another contributing factor: an unprecedented influx of donations from across the country, and continued assistance provided by various organizations. Of that, we should be proud.
国の政治がもたつきながらも、どうにかしのいできたのは被災者のみなさんの忍耐強さと地元自治体の努力があったからだ。さらにもう一つ見逃せない点がある。全国からかつてない巨額の寄付が寄せられる一方、今もさまざまな支援活動が続いていることだ。私たちはそれをもっと誇っていい。
Seventeen years have passed since the Great Hanshin Earthquake struck Kobe and Japan witnessed a full-scale emergence of volunteerism. The range of activities that are now being undertaken by volunteers and organizations -- not limited only to the removal of debris or distribution of food and clothing -- is striking.
「ボランティア元年」と言われた阪神大震災から今年で17年。被災地でがれき処理を手伝ったり、食料や衣料を配るだけでなく、活動範囲の広がりは目を見張るほどだ。
◇官・民の壁を超えて
A major pillar of continued support to disaster-struck northeastern Japan has been nonprofit organizations (NPOs).
その重要な担い手がNPOだ。
Fukushima Kids, for example, offers sleepaway camps for children from Fukushima Prefecture, where the nuclear crisis has yet to be brought under control. The children are invited to stay in Hokkaido and other areas of Japan -- where they are free to play outside without fear of radiation exposure -- during their school holidays. Last summer and this past winter, 518 and 190 children, respectively, participated in the program, away from home and their parents. Preparations are underway for another round during the upcoming spring break. Various NPOs, private companies and local governments have cooperated to make this program possible, and the amount of donations has reached approximately 80 million yen.
例えば、原発事故の影響を今も受ける福島県の子供を夏休みと冬休みの長期間、北海道など各地で受け入れて林間学校を開いた「ふくしまキッズ」。夏は518人、冬も190人の小中学生が親元を離れて参加し、今は近く始まる春休みの準備が進む。多くのNPOと企業、自治体が協力し、これまで集まった寄付金は約8000万円にもなる。
In the program, volunteer college students look after the children on a day-to-day basis. As soon as organizers started seeking volunteers in the spring, some 200 students applied. In addition to college students, some high school students also offer their services, coming in to help when they don't have classes at school.
子供の世話をするのは主に学生ボランティアだ。春の活動にも瞬く間に約200人が応募。大学生だけでなく補習授業の合間に手伝いに来る高校生もいる。
One of the program's founders and its director, Hirohiko Yoshida, 59, recalls the painful memories of trying to set up a similar program when Mount Oyama on Miyakejima Island erupted in 2000, leading to the evacuation of the island's residents. The program did not last long then, and because of this, Yoshida is even more determined to make the current program a success.
発起人の一人、NPO「教育支援協会」の吉田博彦代表理事(59)は、00年の三宅島噴火の時も同じ試みをしながら長続きしなかった苦い経験を持つ。
"We're going to keep this going for at least five years. We can't just complain (and hope that someone else will do something)," Yoshida says. "We want to nurture children who become the future of Fukushima."
それだけに「5年は続ける。誰かに文句を言うだけではいけない。福島の未来を担う子供を育てたい」と話す。
Last summer, Katariba, a nonprofit organization run by people in their 20s and 30s, set up a free "collaborative school" in the Miyagi Prefecture town of Onagawa, which suffered catastrophic damage from the March 2011 tsunami. It hires cram-school teachers who lost their jobs due to the disasters, and is also supported by volunteer college students and former Onagawa residents living in the Tokyo metropolitan area who have taken a leave of absence from their jobs to offer their support. The instructors use empty rooms in an elementary school to teach about 200, or roughly one-third, of the town's elementary and junior high school students.
20代、30代の若者が運営するNPO「カタリバ」は、津波で壊滅的被害を受けた宮城県女川町で昨夏、無料の学習塾「女川向学館」を始めた。小学校の空き教室を利用し、震災で職を失った塾講師を雇用する一方、休職して首都圏から駆けつけた同町出身の会社員やボランティア大学生らが町の小中学生全体の3分の1に当たる約200人を教える。
The key to this set-up is full-on collaboration between the NPO and the Onagawa Municipal Government, as well as the local board of education and schools -- which have traditionally been in competition with so-called cram schools. Parents have also been approaching the group recently to ask how they can help.
女川町役場、そして従来、塾とは競合してきた地元教育委員会と学校が全面的にNPOとコラボ(協同)しているのがミソだ。最近は親たちも「何かできることはないか」と協力を申し出るようになった。
"When the children who have experienced the disasters overcome their hardships, they're going to be stronger and more compassionate than most people," says Katariba director and Tokyo resident Kumi Imamura, 32, who has been spending most of each month in the disaster areas. "Our job is to provide them with learning opportunities that will help them become those people."
東京を離れ、月の大半を現地で暮らすカタリバの今村久美代表理事(32)は「震災の試練を経験した子供たちは、もしそれを乗り越えたなら誰よりも強く優しくなれるはず。私たちの役目はそのための学習機会を作ってあげること」という。
Last December, Katariba opened their second "collaborative school" in the Iwate Prefecture town of Otsuchi. The organization promotes learning without depending entirely on local governments or schools -- a set-up that is slowly beginning to take root.
昨年12月には岩手県大槌町に2校目も開校した。役所や学校任せにしない新しい学びの形が生まれつつある。
Upon learning that autistic children affected by the disasters were having difficulties at evacuation centers, Hiromoto Toeda, 43, director of Musou, a social welfare corporation based in Aichi Prefecture, and Yusuke Ohara, 32, director of nonprofit organization Yuyu based in Hokkaido, moved into action. With volunteer students in tow, they descended upon Tanohata village in Iwate Prefecture, and tried to launch a daycare service for children with disabilities. Iwate prefectural officials, however, were unenthusiastic about the endeavor, saying that there were only five children requesting such care in the entire prefecture.
愛知県半田市の社会福祉法人「むそう」の戸枝陽基理事長(43)と北海道当別町のNPO「ゆうゆう」の大原裕介理事長(32)は震災直後、「自閉症児らが避難所で苦労している」と聞き、学生らを連れて岩手県田野畑村に駆けつけた。障害児や家族を支援する児童デイサービスを始めようとしたが、当初、県の担当者は「県全体でも5人しか希望者がいない」と渋ったという。
However, when Toeda and Ohara began daycare services anyway without the support of local government bodies, over 20 children in a village of around 4,000 people began using them. Users were happy with the program for closely catering to the needs of individual children, leading to the launch of a similar program in the Iwate Prefecture city of Miyako, which also has over 20 participants. Many local residents have said that they were not aware of such programs, and now the local government has changed its position and is set to officially place the programs under its jurisdiction.
ところが戸枝さんらが自主的に活動を始めると人口約4000人の同村だけでも20人以上が利用。障害特性に合った活動が評判を呼び、同県宮古市で始めた事業も20人以上が利用する。地元では「こんなサービスがあるとは知らなかった」と多くの人がいう。今では行政も協力し、近く正式に役所の事業となる予定だ。
◇政治が頼りないのなら
Local governments had heretofore viewed NPOs as contractors, but the growing trend of the private sector taking action ahead of public bodies is hard to ignore.
今まで行政側には「NPOは下請け」の意識があったのは事実だ。だが、こうして「民」が「官」をリードする動きも広がっている。
Due to a law revision last year, taxpayers can get back up to 50 percent of a donation to an NPO from the national or municipal governments. This, too, is a huge step forward.
昨年の法改正でNPO法人に寄付をすれば最大で国や自治体から寄付額の5割近い税金が戻ってくるようになった。これも大きな前進だ。
Collecting taxes and making decisions on how they are used was originally the job of the national and local governments. However, public bodies are not the only ones responsible for the public sector. The involvement of nonprofit organizations into education and social welfare is gradually becoming the norm. Members of the public are increasingly donating money to NPOs that they would prefer to support over public bodies, receiving tax deductions in return. Though still in the beginning stages, this signals an era in which we get to choose how our tax money is spent.
税金を徴収し、使い道を決めるのは従来、政府や自治体の仕事だった。だが、公共を担うのは官だけではない。教育や福祉などNPOの活動は拡大し定着してきている。そんな中、国民それぞれが「役所より、このNPOを応援したい」と寄付をし、減税される。それは一部とはいえ税金の使い道を国民自らが選択できる時代になったことを意味する。
The Japanese government's general account budget is approximately 90 trillion yen. Suppose 10 trillion yen in donations are made in a year, with NPOs taking charge of increasingly more in the public sector without being bogged down by the sectionalism of the bureaucracy, while overcoming community and generational boundaries. Imagine that. The government will slim down considerably, inevitably bringing changes to the Diet.
国の一般会計予算は約90兆円。仮に寄付金が年に10兆円に上り、役所の縦割りや地域、世代の壁を超えてNPOが活躍する社会を想像してみよう。行政は一気にスリム化され、国会もおのずと変容するはずだ。
Let us call this the "NPO revolution." Of course, continued recovery from the triple disasters requires further support from the public. With politics at a standstill, each and every one of us must take action and do what we can. Over the past few years, the idea that others' happiness leads to one's own happiness has been gathering momentum among our youth. This is certainly a foundation on which a revolution can be built.
私たちはこれを「NPO革命」と呼んでみたい。もちろん震災支援を継続させるには、今後ますます国民の後押しが必要だ。しかし政治が立ち止まっているのなら、一人一人が自分のできることから動き始めるしかない。この数年、特に若い世代の間に「他人の幸せになることが自分の幸せになる」という機運が広がっている。「革命」の土壌はある。
We will never forget the day that filled the entire country with untold sadness and shattered our values -- including our belief in the "safety" of nuclear power. From here on out, let us imagine a future in which Japan leads the world in realizing a new "public" society.
日本中が悲しみに包まれ、「原発安全神話」をはじめ、これまでの価値観が崩れ去ったあの日を私たちは忘れない。そして、これからはまったく新しい「公共社会」を日本が実現させて世界をリードする。そんな未来を思い描こう。
毎日新聞 2012年3月11日 2時30分
■近況
2009年の9月15日に脳梗塞を発症、右手が少し不自由になりました。
MRAで脳梗塞の部位を特定でき、素早い処置をとれたので大事に至りませんでした。
快復にむけてリハビリ中です。
(2011/01/01更新)
■自己紹介・リンク
[ はじめに ]
タイのスラチャイです。
英語学習に王道はありません。
毎日毎日の地道な努力の積み重ねが必要です。
スラチャイはNHKのラジオ英語会話で現在の英語力を身につけました。
一日僅か15分の学習でも数年間継続すれば相当な学習効果が期待できます。
[ 名前 ]
松井 清 (スラチャイ)
[ 略歴 ]
・福岡県出身
・国立高知大学卒業
・準大手建設会社に就職
・50歳で会社を早期退職
・99/10 タイ全土を旅行
・00/10 タイに移住
・03/07 カイちゃん誕生
・07/06 シーファーちゃん誕生
・現在タイ国コンケン在住
[ 座右の銘 ]
Slow and steady wins the race.
遅くとも着実な者が勝利する
(NHK基礎英語芹沢栄先生)
[ 学習の手引き ]
・音読して耳から英語を吸収
・Think in English.
・ネイティブ発音付辞書活用
・英英辞典を活用(英和も)
・翻訳和文で専門用語確認
[ English Newspapers ]
Yomiuri
Mainichi
Asahi
Japan Times
Washington Post
Newyork Times
Bangkok Post
The Nations
Phuket Gazette
[ 英字新聞の英和対訳学習 ]
英字新聞(読売)
英字新聞(毎日)
英字新聞(朝日)
英字新聞(朝日2)
[ スラチャイ編集の辞書 ]
タイ日辞書(改訂版)
日タイ辞書(改訂版)
ラオ日辞書
日ラオ辞書
スラチャイの家族紹介
私の家族
スラチャイの手作りリンク集
スラチャイタイ在住9年目
中国語会話基礎(北京語)
タイ日辞典(単語帳)
タイ語の子音
タイ語の母音
スラチャイ編曲のmidiのギター曲
スラチャイ編曲のJ.S.Bachです
スラチャイの多国言語学習
初歩のタイ語
初歩の中国語
初歩のラオス語
初歩のビルマ語
初歩のシンハリ語
初歩のタガログ語
タイ語の基礎
タイ文字
タイ日辞書
タイ語の副詞
タイ語の前置詞
タイ語の助動詞
タイ語の接続詞
基礎タイ語一覧(タイ文字、ローマ字)
seesaaサイト内リンク一覧:
01 あいさつ
02 別れのあいさつ
03 声をかけるとき
04 感謝の言葉と答え方
05 謝罪の言葉と答え方
06 聞き直すとき
07 相手の言うことがわからないとき
08 うまく言えないとき
09 一般的なあいづち
10 よくわからないときの返事
11 強めのあいづち
12 自分について述べるとき
13 相手のことを尋ねるとき
14 頼みごとをするとき
15 申し出・依頼を断るとき
16 許可を求めるとき
17 説明してもらうとき
18 確認を求めるとき
19 状況を知りたいとき
20 値段の尋ね方と断り方
21 急いでもらいたいとき
22 待ってもらいたいとき
23 日時・場所・天候を尋ねるとき
24 その他
基礎タイ語一覧(タイ文字、音声付き)
サイト外HPリンク一覧:
01 あいさつ
02 別れのあいさつ
03 声をかけるとき
04 感謝の言葉と答え方
05 謝罪の言葉と答え方
06 聞き直すとき
07 相手の言うことがわからないとき
08 うまく言えないとき
09 一般的なあいづち
10 よくわからないときの返事
11 強めのあいづち
12 自分について述べるとき
13 相手のことを尋ねるとき
14 頼みごとをするとき
15 申し出・依頼を断るとき
16 許可を求めるとき
17 説明してもらうとき
18 確認を求めるとき
19 状況を知りたいとき
20 値段の尋ね方と断り方
21 急いでもらいたいとき
22 待ってもらいたいとき
23 日時・場所・天候を尋ねるとき
24 その他
タイの文化一覧:
01 雨の日にも傘をささないタイ人
02 勉強熱心なタイ人女性たち
03 タイ人は敬謙な仏教徒
04 タイの市場
05 タイの食堂
06 タイ人は外食が大好き
07 果物王国タイランド
08 タイ人の誕生日
09 タイの電話代は高い
10 微笑みの国タイランド
14の戒律(テラワーダ仏教戒律)
seesaaサイト内リンク一覧:
第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律
14の戒律(テラワーダ仏教戒律)
サイト外HPリンク一覧:
14の戒律解説
第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律