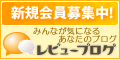[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Kaleidoscope of the Heart: A lesson in occupational health
香山リカのココロの万華鏡:産業保健の講座受講 /東京
There is a field of medicine called occupational health, which involves protecting the health of people working in companies and organizations.
医学の中に、企業や組織などで働く人たちの健康を守る産業保健という分野がある。
Recently I made up my mind to take part in a one-week intensive summer course at the University of Occupational and Environmental Health.
一念発起して、産業医大で行われている1週間の夏季集中講座に参加した。
The program included statistics, ergonomics and training involving electrocardiograms and other issues that I'm not too good with, so I felt relieved when the topic of mental health came up.
統計学や人間工学、心電図など苦手な分野の講習が続く中、唯一ほっとできるのはメンタルヘルス系の科目だ。
Saying I'm relieved with talk about depression may sound strange, but being a psychiatrist, I guess that's where I fit in.
「うつ病の話にほっとする」などというのはおかしな表現だが、やっぱりこれが自分の居場所ということなのだろう。
In a lecture by Jun Nakamura of the university's Department of Psychiatry, one particular phrase that struck me was: "Psychiatric health in modern Japan is an economic issue."
産業医大精神科の中村純教授の講義で印象に残ったのは、「現代日本の精神保健は、経済問題」というフレーズだった。
In other words, the "emotional problems" that are in the spotlight in present-day Japan are intertwined with economic issues and changes in social structure at some point along the line.
つまり、いまの日本でクローズアップされている「心の問題」は、いずれもどこかに経済の問題や社会構造の変化が関係している、ということだ。
It's true that there is a lot of stress in companies today, with harsh personnel evaluations, a doctrine of competitiveness, and corporate restructuring that could happen any moment.
たしかに、会社に目をやると厳しい人事評価や競争主義、いつ宣告されるかわからないリストラ、などストレスがいっぱい。
At the same time, job hunting is also becoming tougher for students and some have no option but to become part-time job hoppers or NEETs -- those not in education, employment or training.
さらに学生の就職活動は過酷になるばかりで、その結果、仕事につけずにフリーターやニートにならざるをえない若者もいれば、
Others go from one temp job to another and end up losing both their work and their families.
派遣労働を転々として、最終的に仕事も家も失ってしまう人さえいる。
But since other people are busy looking out for number one, no one lends a helping hand.
そうなっても、誰もが自分のことで精いっぱいなので、助けの手もさしのべられない。
In other words, people in society today can't feel at ease whether they are in an organization or not.
つまり、いまの社会では人は組織にいてもいなくても、安心して暮らすことができない、ということだ。
Stress levels rise in an atmosphere of uneasiness and tension, and there is no doubt people who suffer from depression and other conditions as a result.
不安や緊張の中でストレスが高まり、うつ病などになる人も当然、増えるだろう。
However, no matter how much psychiatrists call for revision of the nation's economic structure, society will never change overnight.
とはいえ、精神科医がいくら「経済構造を見なおせ」などと声を上げても、すぐに社会が変わるわけではない。
Accordingly, there is no option but to handle the situation with preventive measures within the community and companies, and with treatment in consultation rooms.
そうであれば、まずは地域や企業では予防を、診察室では治療を、という地道な作戦しかない。
Professor Nakamura says that when someone in an organization takes leave due to depression or some other reason, he wants the person and those around that person to find significance in the event upon their return to work.
中村教授は、組織でうつ病などで休職した人が出た場合は、その復職にあたって本人もまわりも病気の経験に意義を見いだせるようにしてほしい、と語った。
In one cited example, when a worker succumbed to depression, the person's department looked back on its approach to work, and decreased overtime and provided more opportunities for communication.
たとえば、うつ病になる人が出たことで、その部署がこれまでの働き方を振り返り、残業を減らしたりコミュニケーションの機会を増やしたりした。
The person who had fallen ill also made an effort to increase family time.
本人も、家族とすごす時間を増やすように生活を工夫した。
If such an approach can be adopted, then it should be possible for the person to say, "It was good that I had depression."
もしそうできたら、まさに「うつ病になってよかった」ということになるはずだ。
I had secretly thought that if occupational health was really interesting, then I might change jobs, but what I learned from taking part in the course was that it was good I became a psychiatrist.
「産業保健があまりに面白かったらこっちに転職しようかな」とひそかに思っていた私だが、この講座で学んだことは「精神科医になってよかった」ということ。
I will now aim to become a doctor whose patients can think, "I got ill but there were some good things about that."
これからは患者さんに、「病気になったけれど、よかったこともあった」と思ってもらえるような医者を目指すことにしよう。
毎日新聞 2011年8月2日 地方版
■近況
2009年の9月15日に脳梗塞を発症、右手が少し不自由になりました。
MRAで脳梗塞の部位を特定でき、素早い処置をとれたので大事に至りませんでした。
快復にむけてリハビリ中です。
(2011/01/01更新)
■自己紹介・リンク
[ はじめに ]
タイのスラチャイです。
英語学習に王道はありません。
毎日毎日の地道な努力の積み重ねが必要です。
スラチャイはNHKのラジオ英語会話で現在の英語力を身につけました。
一日僅か15分の学習でも数年間継続すれば相当な学習効果が期待できます。
[ 名前 ]
松井 清 (スラチャイ)
[ 略歴 ]
・福岡県出身
・国立高知大学卒業
・準大手建設会社に就職
・50歳で会社を早期退職
・99/10 タイ全土を旅行
・00/10 タイに移住
・03/07 カイちゃん誕生
・07/06 シーファーちゃん誕生
・現在タイ国コンケン在住
[ 座右の銘 ]
Slow and steady wins the race.
遅くとも着実な者が勝利する
(NHK基礎英語芹沢栄先生)
[ 学習の手引き ]
・音読して耳から英語を吸収
・Think in English.
・ネイティブ発音付辞書活用
・英英辞典を活用(英和も)
・翻訳和文で専門用語確認
[ English Newspapers ]
Yomiuri
Mainichi
Asahi
Japan Times
Washington Post
Newyork Times
Bangkok Post
The Nations
Phuket Gazette
[ 英字新聞の英和対訳学習 ]
英字新聞(読売)
英字新聞(毎日)
英字新聞(朝日)
英字新聞(朝日2)
[ スラチャイ編集の辞書 ]
タイ日辞書(改訂版)
日タイ辞書(改訂版)
ラオ日辞書
日ラオ辞書
スラチャイの家族紹介
私の家族
スラチャイの手作りリンク集
スラチャイタイ在住9年目
中国語会話基礎(北京語)
タイ日辞典(単語帳)
タイ語の子音
タイ語の母音
スラチャイ編曲のmidiのギター曲
スラチャイ編曲のJ.S.Bachです
スラチャイの多国言語学習
初歩のタイ語
初歩の中国語
初歩のラオス語
初歩のビルマ語
初歩のシンハリ語
初歩のタガログ語
タイ語の基礎
タイ文字
タイ日辞書
タイ語の副詞
タイ語の前置詞
タイ語の助動詞
タイ語の接続詞
基礎タイ語一覧(タイ文字、ローマ字)
seesaaサイト内リンク一覧:
01 あいさつ
02 別れのあいさつ
03 声をかけるとき
04 感謝の言葉と答え方
05 謝罪の言葉と答え方
06 聞き直すとき
07 相手の言うことがわからないとき
08 うまく言えないとき
09 一般的なあいづち
10 よくわからないときの返事
11 強めのあいづち
12 自分について述べるとき
13 相手のことを尋ねるとき
14 頼みごとをするとき
15 申し出・依頼を断るとき
16 許可を求めるとき
17 説明してもらうとき
18 確認を求めるとき
19 状況を知りたいとき
20 値段の尋ね方と断り方
21 急いでもらいたいとき
22 待ってもらいたいとき
23 日時・場所・天候を尋ねるとき
24 その他
基礎タイ語一覧(タイ文字、音声付き)
サイト外HPリンク一覧:
01 あいさつ
02 別れのあいさつ
03 声をかけるとき
04 感謝の言葉と答え方
05 謝罪の言葉と答え方
06 聞き直すとき
07 相手の言うことがわからないとき
08 うまく言えないとき
09 一般的なあいづち
10 よくわからないときの返事
11 強めのあいづち
12 自分について述べるとき
13 相手のことを尋ねるとき
14 頼みごとをするとき
15 申し出・依頼を断るとき
16 許可を求めるとき
17 説明してもらうとき
18 確認を求めるとき
19 状況を知りたいとき
20 値段の尋ね方と断り方
21 急いでもらいたいとき
22 待ってもらいたいとき
23 日時・場所・天候を尋ねるとき
24 その他
タイの文化一覧:
01 雨の日にも傘をささないタイ人
02 勉強熱心なタイ人女性たち
03 タイ人は敬謙な仏教徒
04 タイの市場
05 タイの食堂
06 タイ人は外食が大好き
07 果物王国タイランド
08 タイ人の誕生日
09 タイの電話代は高い
10 微笑みの国タイランド
14の戒律(テラワーダ仏教戒律)
seesaaサイト内リンク一覧:
第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律
14の戒律(テラワーダ仏教戒律)
サイト外HPリンク一覧:
14の戒律解説
第01番目の戒律
第02番目の戒律
第03番目の戒律
第04番目の戒律
第05番目の戒律
第06番目の戒律
第07番目の戒律
第08番目の戒律
第09番目の戒律
第10番目の戒律
第11番目の戒律
第12番目の戒律
第13番目の戒律
第14番目の戒律